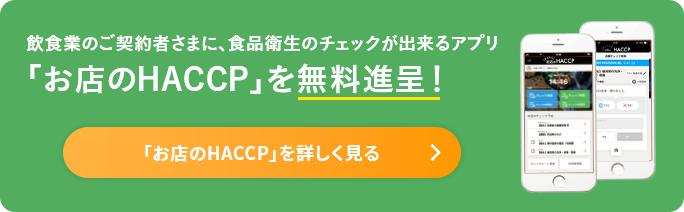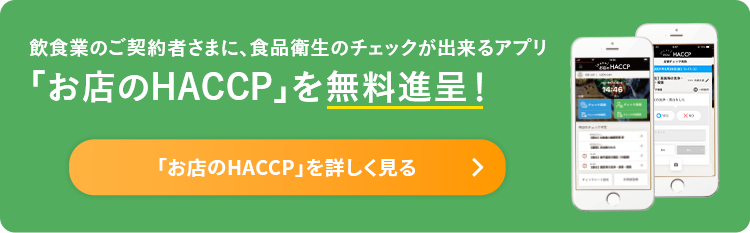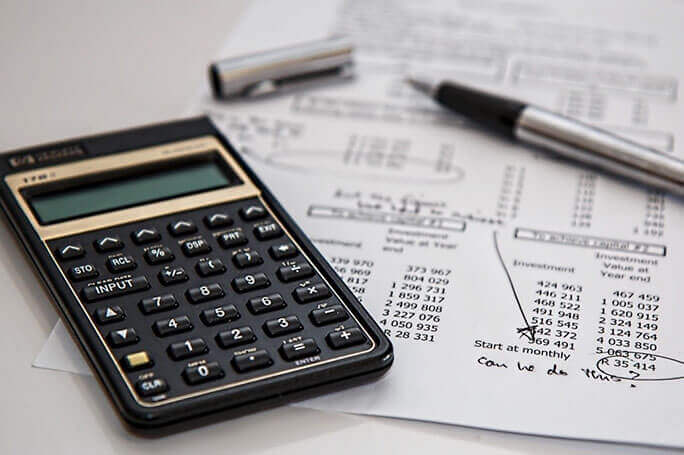2021年6月1日から義務化。HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理とは?
HACCP
2021.05.19

2021年6月1日より、食品等を扱う全事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられます。なぜ実施しないといけないのか、実際にどのように管理すればいいのかを始め、簡単にできる管理方法などをお伝えします。
HACCP(ハサップ)とは?
HACCPとは、全ての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)が、食品の安全を確保するために、原材料の入荷から製品の出荷までの全工程を管理するシステムのことで、「Hazard(危害), Analysis(分析), Critical(重要), Control(管理), Point(点)」の頭文字を組み合わせてできた名称です。
食品等事業者が自ら食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握し、その要因を除去又は低減させるために、特に重要な工程を継続的に監視・記録します。
(1)HACCPによる管理工程例
原材料の入荷から、製品の出荷までの工程の中で、どのような流れで管理していくのか、例を見ていきましょう。
- 〇HACCP(ハサップ)による管理の例
- 1.原材料入荷:受入検査・記録
- 2.保管:調合比率、温度、充填、密閉性、全ての確認・記録
- 3.熱処理:殺菌温度や時間を継続的に監視して記録
- 4.冷却:水質や水温の確認・記録
- 5.包装:異物の検出、衝撃、温度の確認と記録
- 6.出荷
(2)従来の検査との違い
HACCPによる衛生管理方法の導入が行われるまでは、最終製品の抜取検査が品質管理の主流でした。この場合、もし不適合な製品が見つかると、一連の全ての製品の廃棄が必要ですが、HACCPによる工程管理を行っていれば、記録をもとに原因を追究し、効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことができます。
(3)HACCP導入義務化対象外について
原則、全ての食品等事業者はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要ですが、一部対象外の事業者もあります。まずは、自社がHACCPの導入が必要かどうかの確認をおこないましょう。
HACCP(ハサップ)は実施しなければならないの?
HACCP(ハサップ)は、なぜ実施しなければならないのでしょうか?また、どのように導入して進めていけばよいのでしょうか?導入する理由や方法などをお伝えします。
(1)なぜ実施しなければならないのか
厚生労働省によると、食中毒の発生件数が近年下げ止まりの傾向にあることや、異物混入による食品回収事例の告知件数の増加により、衛生管理手法の国際標準であるHACCPの普及が必要とされています。
アメリカではHACCPによる衛生管理は2011年より義務付けされており、その後、先進国を中心に義務化が進んでいます。日本から輸出する食品にも要件とされているため、日本の食品等事業者もHACCPによる衛生管理に取り込み、食品の安全性を高めることが必要となります。
(2)実施しなければどうなる?
HACCP(ハサップ)の導入にあたり、認証の取得は必要ありません。つまり、HACCPに沿った方法で衛生管理をしていれば、導入していることになります。また、HACCPを導入しなかった場合の罰則は2021年4月末時点では設けられていません。ただし、食品衛生法では営業許可の取消や営業禁停止については、都道府県が判断することとなっており、一般的には改善のための行政指導が行われます。従わない場合は、改善が認められるまでの間、営業禁停止などの行政処分が行われる可能性があります。
なお、飲食店が万一HACCPに沿った衛生管理を行っていない事業者から仕入れた食材を使用した場合、そのような事業者から材料等を購入したことが直ちに食品衛生法の違反になるものではありませんが、受入時には検査や確認を行うようにしましょう。
(3)HACCPの7原則12手順とは
HACCP(ハサップ)の導入には、7原則を含む12の手順に沿って進めていきます。手順1~5は原則1~7を進めるための準備段階です。
- 〇HACCPの「7原則12手順」
- 手順1:HACCPチームの編成
- 手順2:製品についての記述
- 手順3:意図する用途の特定
- 手順4:製造工程一覧図の作成
- 手順5:製造工程一覧図の現場での確認
- 手順6(原則1):危害要因の分析
- 手順7(原則2):重要管理点の決定
- 手順8(原則3):管理基準の設定
- 手順9(原則4):モニタリング方法の設定
- 手順10(原則5):改善措置の設定
- 手順11(原則6):検証方法の設定
- 手順12(原則7):記録の保持
HACCP(ハサップ)の対応はアプリが便利
(1)事業者の規模に応じた管理基準
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理は、原則、全ての食品等事業者に実施が義務付けられますが、大規模事業者と小規模事業者とでは資金面等で差があるため、それぞれに応じた基準が設けられています。
- ○事業者の規模に応じた基準
- ・従業員数が50名以上の大規模事業者
HACCPに基づく衛生管理:事業者自らが使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う。 - ・従業員数が50名未満の小規模事業者
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理:公益財団法人日本食品衛生協会などが業種ごとに作成した手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
手引書に沿って実施することで、HACCPによる衛生管理を実施していることになるため、比較的小規模事業者は導入しやすくなっています。
- ○小規模事業者が実施すること
- 1.手引書の解説を読み、自分の業種・業態では何が危害要因となるかを理解する
- 2.手引書のひな型を利用して、衛生管理計画と必要に応じて具体的な方法を定めた手順書を準備する。
- 3.従業員に周知徹底を図る
- 4.手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、手引書で推奨された期間、保存する
- 5.記録や効果を定期的に振り返り、必要に応じて内容を見直す
(2)アプリで簡単管理
小規模事業者は、手引書に沿って衛生管理を進めてくことでHACCP(ハサップ)を導入していることになりますが、衛生管理の記録や書類の保管には手間がかかり、後で見直すのも大変です。その手間を少しでも減らすために、アプリを利用すると便利で簡単です。
- 〇HACCPアプリ(「お店のHACCP」など)でできること
- ・あらかじめ用意されたテンプレートから必要な項目を選択するだけで、衛生管理計画を簡単に作ることができます。
- ・登録したチェックポイントをタップしていくだけで、衛生管理を記録することができ、保存もできます。
- ・記録したデータをいつでも確認することができます。
アプリの利用は代表者だけでなく、業務に携わるスタッフを登録することもでき、事業者全員で管理することが可能です。
(3)さらに保険で備える
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理をすることで、食中毒の発生を抑える効果は期待できますが、発生した食中毒に対しては備えられていません。万一食中毒が発生したら、お客様への治療代や入院・通院代などの支払いが発生するうえ、営業停止となった場合、その期間は収入がなくなります。お客様への賠償費用やお店の損失に備えて、保険に加入しておくとより安心です。
HACCP(ハサップ)が義務化されることにより、食品等事業者の衛生管理に対する意識がより高まり、食中毒や異物混入等を減らす効果が期待されます。負担なくHACCPの対応を進めていくためにアプリの利用を検討しましょう。
店舗保険のお役立ち情報
保険料シミュレーション
業種別にさまざまなプランの保険料をシミュレーションすることができます。
最新のお役立ち情報

保険事故対応の流れを徹底解説!店舗保険で起きた損害をカバー
店舗保険

店舗向け火災保険の相場は?保険料を抑えるためのポイントも解説
店舗保険

知っておきたい!個人事業主の賠償トラブルを防ぐ保険の基本
損害賠償責任

企業向けカスハラ保険とは?導入のメリットと選び方を解説
トラブル・リスク

スナックやバーなどのナイト店は加入できる?店舗保険のメリットを徹底解説
店舗保険

フリーランスでも入るべき! 美容院・サロンの賠償保険
損害賠償責任

知らぬ間にHPが改ざんされた時に、お客様を守る方法
トラブル・リスク

そのメール、開封して大丈夫?標的型攻撃メールの見分け方と対処法
トラブル・リスク

注意しただけなのに・・・。新入社員にパワハラと思われる上司の言動と行動
トラブル・リスク

あなたの言動は大丈夫?職場での妊婦さんへの接し方
トラブル・リスク
保険について
飲食業のご契約者さまに
「お店のHACCP」を無料進呈!

厚生労働省が推奨する、HACCPガイドライン※に準拠
従業員50人未満の店舗であれば、このアプリで対策が可能です
必要なものはスマートフォンのみ
かんたん設計で今すぐご利用が可能です
クラウド上で一元管理
サーバー上で8年間保存ができ、いつでも情報を取り出せます